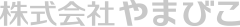「驚き」ふたたび
共立スピードスプレーヤ 発売60周年
1957年、長野県のりんご栽培農家に国産初のスピードスプレーヤが導入されました。人工的に発生させた風力を利用して短時間に薬剤散布するという光景を初めて目にした先人たちの驚きは想像に難くなかったことでしょう。以来、先進の防除性能と作業性にこだわって進化を深めた共立スピードスプレーヤは、2017年には発売60周年を迎えます。待望の600Lキャビンモデルもいよいよ登場。60年目の「驚き」をお届けします。

1957年 国産初のスピードスプレーヤ発売
1955年。スピードスプレーヤが初めて日本に導入。北海道余市町のりんご園経営者がアメリカのFMC・ジョンビーン社から輸入したものであった。当社は、これを見学、基本的な機構を参考にしながら、直ちに設計試作に取り組んだ。そしてスピードスプレーヤ「SS-1型」を開発、発売したのは、1957年5月のことであった。試作機1号機は、長野県小布施町のりんご園経営者のもとへ搬入され、当初はけん引車としてトラクターを採用。当時の果樹栽培は、防除と収穫が全労働時間の50%を占めていたので、スピードスプレーヤの導入は、生産性の向上に大いに役立ち、同時に品質の向上、経営の近代化に貢献した。
1965年 自走式スピードスプレーヤ誕生
わが国の果樹経営近代化の推進力となり、数々の奇蹟を生んできた共立スピードスプレーヤ。「SS」は従来の動噴にくらべて薬剤費は1/2以下、人手は1/25以下で済むうえ、大面積画一共同防除による防除効果の増大や果実の品質向上ができるなど、驚異的な生産性向上をもたらした。しかし、これまで販売していた「牽引式」では山間部などの日本特有の圃場では「小回り旋回性」の面で大きな欠点が指摘されていた。そこで、当社は1965年に傾斜地果樹園むけに開発された新しい構想の自走式SS「SSV-70」を発売。走行用・散布用にそれぞれ独立した2つのエンジンを持ち、走行速度によって散布能力が落ちたりする心配がなく、効率の高い散布作業が可能になった。

1994年 誘導ケーブル式無人スピードスプレーヤ
スピードスプレーヤの普及により作業効率は飛躍的に高まったが 夏場の防除は作業者の労働強度が著しく高く、 また共同防除組織も高齢化とオペレータ不足による組織の再編など、 様々な問題が見られるようになった。それに応えるべく1993年には農業機械促進法が一部改正され、「農業機械などの緊急開発事業」がスタートした。当社は国と共同で無人防除機の開発を緊急開発事業により進め、誘導ケーブル式無人スピードスプレーヤの製品化に成功した。

2000年 共立初のキャビン型スピードスプレーヤ
自走式スピードスプレーヤの誕生から35年後の2000年。多くの『SS』ユーザーの声に応え、共立初のキャビン型スピードスプレーヤSSV1088FSCが登場。飛散する薬液から作業者を守り、作業空間を快適に保つ「エアコン」装備のキャビンタイプ登場で、夏場における過酷な防除作業の負荷軽減に貢献。さらに、キャビン部はSS使用中の転倒などからオペレータを保護する観点で頑強な「フレーム構造」を採用。キャビン室内から操作できる「4輪操舵切り替え」「送風機」「薬液ポンプ」の各スイッチを前面パネルにレイアウトすることで、運転席での快適な操作性を追求。共立スピードスプレーヤの代表作となった。

2015年 世界初!電動式スピードスプレーヤを発売
少子高齢化や若者の農業離れが進み、かつては実り豊かな圃場も隣接地の宅地化が進み、農業機械から発生する騒音に関するSSユーザーの悩みが多く寄せられるようになった。都市部の農業経営者は近隣住民に気を遣い、早朝作業を遠慮しながらの作業も散見される。都市型農業を継続し、共存共栄していくには低騒音かつECOな農業機械の普及が急務であった。当社は100%電気で駆動する「電動式スピードスプレーヤ」を開発。一つのバッテリーで「走行用駆動モーター」と「送風用モーター」を同時制御。低騒音かつECOなスピードスプレーヤが誕生。都市型農業に対する新たな提案となった。

2023年 保護フレーム付スピードスプレーヤ誕生
現代の果樹防除の高能率化には欠かせない存在となったSS。そこで共立は作業者の安全を第一に考え、業界に先駆け「保護フレーム」、そして「シートベルト」が標準装備されたスピードスプレーヤを発売。このフレームはトラクターの安全フレーム規格(ROPSコード?)に準ずる強度基準が満たされていることが確認されており、作業者ファーストな一台となった。 農業の発展と作業者の安全を願う共立だからこそ、作り上げることができた新たなSS。「驚き」の磨き上げはこれからも続いていく。保護フレーム付きスピードスプレーヤ

SSV5150F
薬液タンク500Lモデル。エンジン出力:16.7kW、ポンプ吐出量:60L/min、使用時風量:500?/min。180°回転してノズルを切り替えられる「スイッチノズル」。風切り音を軽減し、低層音で大風量を実現する「新送風システム」。コックの開閉だけでタンク排水ができ、株元への灌水作業にも便利な「ワンタッチドレン」搭載機種。
SSV6150F
薬液タンク600Lモデル。エンジン出力:17.0kW、ポンプ吐出量:88L/min、使用時風量:500?/min。180°回転してノズルを切り替えられる「スイッチノズル」。風切り音を軽減し、低層音で大風量を実現する「新送風システム」。コックの開閉だけでタンク排水ができ、株元への灌水作業にも便利な「ワンタッチドレン」搭載機種。